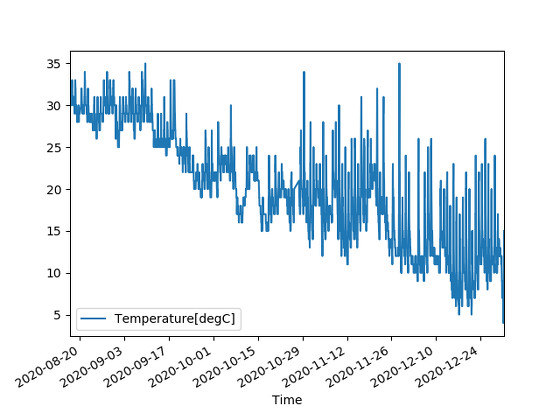ボートスクール受講編からの続き。
【学科試験】
悪天候で実技講習を受けられないまま、学科試験だけを受験。一応科目合格は2年間有効とのこと。まあ何度もチャレンジするような資格ではないとは思うけど。受験者は私とかんなさんともう1名。
身体検査は視力検査(矯正視力)、色覚検査(赤緑白の点を識別する)と、大きな病気などがないか聞かれて終わり。
試験は50問で試験時間は70分。終わったら途中退席OKで、私は3人の中では最後に35分くらいで退席。試験問題は持ち帰り可。全員退席するとすぐに解答が貼り出されて自己採点できる。問題集を一通りやったおかげで私はパーフェクト。かんなさんは何問か間違えたけれど、余裕で合格点。
ちょっと迷った問題は2問。
問10 小型船舶操縦士の免許について述べた次の文のうち、正しいものはどれか。(船舶職員及び小型船舶操縦者法)
- (1) 一級小型船舶操縦士の免許は、全ての小型船舶に船長として乗船できる。
- (2) 水上オートバイを操縦するには、二級小型船舶操縦士以上の免許が必要である。
- (3) 二級小型船舶操縦士の免許は、平水区域及び海岸から5海里以内の水域を航行できる。
- (4) 一級小型船舶操縦士の免許は、満16歳以上であれば取得できる。
問題集にはなかった問題。これは(1)と(3)で迷った。(3)は明らかに正しいのでこれを選んで正解。(1)はどこが誤りなんだろう。特殊小型船舶が操縦できないこと?それともプレジャーボートで全長が24m以上の小型船舶がある?
問28 錨泊中に走錨していると判断できる状態は、次のうちどれか。
- (1) アンカーロープが張ったりゆるんだりする。
- (2) 風を常に片舷方向から受けている。
- (3) 船体が、ほぼ規則的に振れ回っている。
- (4) アンカーロープに触っても、振動が感じられない。
これも問題集にはなかったと思う。(2)と(4)で迷った。風が吹けばアンカーを中心に振れ回るので、片舷方向から風を受け続けるのはおかしいので(2)が走錨ということになる。
試験後は実技試験を様子を遠くから見学。ちょうど風もなく良いコンディションだったので、自分たちも今日が良かったと思ったけれど仕方がない。
語呂合わせで覚えた中では、Isoの灯質を選ぶ問題が出た。
【実技試験】
延期になった実技講習の一週間後が実技試験。コンテストの移動運用と実技講習で寒いところで長時間過ごしたのが祟って、実技講習後から風邪の症状。喉の痛みと咳程度だったので甘く見て在宅で仕事を続けていたら、実技試験2日前に37.5度の発熱。どうにか試験当日には微熱まで下がったけれど、危なかった。
試験艇は講習と同じ(FR23)だけど、学科も実技も試験官はJMRAから派遣されてきて、講習の講師と違うので緊張感はけっこうある。試験当日は快晴で風速は弱いものの、講習時と風向が変わって、桟橋と平行に岸に向かって吹く風。講習では桟橋に押し付ける強い風だったので、この違いがどう効いてくるか。
教室で軽く試験の流れだけ説明があって、すぐにライフジャケットを着て乗船。カンニング防止ということだと思うけれど、手ぶらで乗船するように指示があった。だんだん風が強くなる予報だったので、先に操船、最後に点検という順番。
試験官の操船で沖に出て、クラッチレバーの操作とハンドルを回してロックトゥーロックを試させてもらえる。これは採点と関係ないので、レバーの中立の入り具合とハンドルのセンターを良く確認しておくと良い。
試験が始まると微速発進から指定回転数で直進、滑走と変針、停止して人命救助、方位測定、後進を次々と指示されて操船。それぞれをかんなさんと交代しながら実施。操縦者を交代するたびにハンドルとレバーを消毒してくれていた。
私は方位測定のときコンパスの紐を手首に通すのを忘れてしまった。やっぱり何か抜ける。かんなさんは人命救助で左舷から救助しますと宣言したけれど、ブイが右に流れてしまって右舷から救助。
ブイのところまで移動してもらって、蛇行と避航。これは二人とも問題なし。
位置を合わせてもらって左舷着岸・係留・解らん・後進離岸。私はなんとか着岸できたけれど、かんなさんは舵を切るのが早すぎて着岸できず、試験官が着岸してくれて係留。
試験官は操船方法を指示してくれることはないけれど、明らかに間違った操船をすれば「間違ってますよ」と指摘してくれる。また、安全確認や操作の開始、終了を声を出して宣言すれば、「いいですよ」とか「どうぞ」とか返してくれるので、しつこいくらいに声を出しておくのが良いかも。
それぞれ終わってから点検項目。かんなさんは船体安定、バッテリー、メインスイッチ、バケツとあかくみ、ワイパーを点検、トラブルシュート(スターターは回るけどエンジンがかからず、プライマリポンプは固かった、で、答えはガソリンがない)をしてから機関始動・暖機運転・停止。私は船体外板、浸水、燃料フィルタ、燃料コック、ライフブイ、信号紅炎の点検。トラブルシュートはスターターが回らなくて、バッテリー容量は正常。答えは中立になっていない。をしてから機関始動・暖機運転・停止。
という感じで、乗船から2人合わせて50分ほどで試験は終了。試験官からは良かったとか悪かったとかのコメントはなく、着岸失敗したかんなさんは合格発表までやや不安な日々を過ごした。配点を考えると着岸を丸々落としても他の操船ができていれば十分合格点にはなりそう。実際は操船の出来不出来はそれほど重視されず、安全確認をしっかりやっているかどうかが大きいらしい(参考動画)。
結果はめでたく2人とも合格。合格率95%とも言われていて、そうそう落ちないだろうなとは思う。だとしても、やっぱり一度も触ったことのない状態で動画だけで独学して一発試験を受ける勇気はなかったかも。資格を取ってガンガン船を運転しようと思っている場合はともかく、自分たちみたいに当面乗船の予定がない場合は、単純に講習と試験で2日間船に乗らせてもらえる機会として楽しめると考えれば、そう高いものでもないと思う。ヨットハーバーを見学に行ってから4ヶ月弱と、新型コロナと天候の影響でずいぶん時間を要したけれど、無事に取得できて良かった。そのうち余裕ができたらレンタルで船に乗ってみたい。